国民健康保険税
国民健康保険は病気やけがに備えて、みなさんがお金を出し合い、お医者さんなどにかかった時の医療費(自己負担分以外)の給付や出産育児一時金、葬祭費などの給付にあてる助け合いの制度です。
こうした国民健康保険の給付は、国などからの補助金とともに、みなさんが納める国民健康保険税が大きな財源となっています。
みなさんが安心して医療を受けられるようにするためにも、保険税の納付にご理解とご協力をお願いします。
国民健康保険税を納める義務は、世帯主にあります。
国民健康保険税は、世帯ごとに計算され、世帯主名義で課税されます。
世帯主が国民健康保険の被保険者ではない場合でも、世帯内に国民健康保険の被保険者がいれば、世帯主が国民健康保険税を納めなくてはなりません。
算定方法について
国民健康保険税は、以下を計算、端数処理し、合計したものとなります。
- 基礎分(国民健康保険の保険負担分などになるもの)
- 後期高齢者支援金分(75才以上の方が加入している後期高齢者医療保険へ支援金として、後期高齢者医療保険以外の医療保険に加入している方が負担するもの)
- 介護分(40才〜64才の方が負担する介護保険料で、加入している医療保険と合わせて納付するもの)
| 区分 | 基礎分 | 支援金分 | 介護分 40才~64才 |
算定の方法など |
|---|---|---|---|---|
| 所得割額 | 7.0% | 1.5% | 1.0% | 被保険者の前年の所得金額に応じて計算 (前年の総所得金額−基礎控除額) × 税率 |
| 均等割額 | 17,000円 | 11,000円 | 15,000円 | 被保険者1人あたり |
| 平等割額 | 30,000円 | − | − | 1世帯あたり |
| 課税限度額 | 660,000円 | 260,000円 | 170,000円 | 課税の上限額 |
- (注意1) 国民健康保険税の最高課税限度額は、1,090,000円です。
- (注意2) 国民健康保険税は、前年(1月〜12月)の所得をもとに計算されます。
- (注意3) 年度の途中で国民健康保険に加入した場合は、加入した月から計算し、年度の途中で脱退した場合は、脱退した月の前月分(1日に脱退した場合は、前々月分)までで計算します。
なお、加入・脱退は届出日ではないことにご注意ください。届出が遅れた場合でも、加入・脱退された月にしたがって課税されます。
所得に応じた軽減
世帯の所得が国の定める所得基準を下回る場合、保険税の内、均等割額と平等割額が軽減されます。
ただし、世帯主と被保険者全員が所得の申告をしていない場合、軽減の対象にならないことがあります。
| 保険税が軽減される世帯区分 | 軽減の内容 |
|---|---|
| 前年の所得が43万円+10万円×(給与所得者の数(注釈1)−1)以下の世帯 | 均等割額と平等割額の7割が軽減されます。 |
| 前年の所得が43万円+(30.5万円×被保険者数+10万円×(給与所得者の数(注釈1))−1))以下の世帯 | 均等割額と平等割額の5割が軽減されます。 |
| 前年の所得が43万円+(56万円×被保険者数+10万円×(給与所得者の数(注釈1))−1))以下の世帯 | 均等割額と平等割額の2割が軽減されます。 |
(注釈1) 一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等の支給(60万円超(65歳未満)又は110万円超(65歳以上))を受ける者
- 前年の所得とは、前年(1月〜12月)の世帯主と被保険者全員の所得の合計額 (65才以上の公的年金所得は15万円を控除した額、専従者控除は適用前の金額、分離譲渡所得は特別控除前の金額)です。
- 被保険者数とは、国保被保険者と国保から後期高齢者医療制度へ移行した人の合計人数です。
- 所得に応じた軽減の判定は、賦課期日(4月1日)現在または、国保世帯発生時です。
未就学児の減免
国民健康保険に加入している未就学児(6歳に達する日以降の最初の3月31日以前である被保険者)の保険税のうち、均等割額の5割が軽減されます。
また、所得に応じた軽減が適用される世帯の場合、当該軽減後さらに均等割額が5割軽減されます。
7割軽減世帯の未就学児の場合、残り3割の5割軽減ということで8.5割軽減となります。
5割軽減世帯の未就学児の場合、残り5割の5割軽減ということで7.5割軽減となります。
2割軽減世帯の未就学児の場合、残り8割の5割軽減ということで6割軽減となります。
旧被扶養者の減免
国民健康保険の被保険者のうち、次の3点すべてに該当する方は、減免を受けることができます。
- 国民健康保険の被保険者の資格を取得した日に65才以上である方
- 国民健康保険の被保険者資格を取得した日の前日に被用者保険の被扶養者であった方
- 国民健康保険の被保険者資格を取得した日の前日に扶養関係にあった被用者保険の被保険者本人が、その翌日に後期高齢者医療被保険者となった場合
減免の内容
- 旧被扶養者に係る所得割額を免除します。
- 旧被扶養者に係る均等割額を、資格を取得した月から2年を経過する月までの期間、半額となるよう減額します。
- 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額を、資格を取得した月から2年を経過する月までの期間、半額となるよう減額します。
産前産後期間の軽減制度
出産した被保険者の国民健康保険税が一定期間軽減されます
子育て世代の負担軽減や次世代育成支援の観点から、国民健康保険の被保険者が出産した場合、産前産後の一定期間の国民健康保険税が軽減されます。
軽減制度の適用には、原則として届出が必要となりますのでご注意ください。
対象となる方
令和5年11月1日以降に出産または出産予定の、東庄町国民健康保険の加入者の方
(注意)出産とは妊娠85日以上の分娩をいい、死産、流産(人工妊娠中絶を含む。)及び早産の場合も対象となります。
軽減される期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間)の国民健康保険税が軽減されます。
(注意)軽減の対象となるのは、令和6年1月分以降の国民健康保険税です。

届出時期
出産予定日の6か月前から届出できます。出産後の届出も可能です。
届出に必要なもの
届出に必要なものは以下のとおりです。
- 産前産後期間に係る保険税軽減届出書.pdf(PDFファイル:74.7KB)
- 出産予定日(出産日)及び単胎妊娠または多胎妊娠の別が確認できる書類(母子手帳など)
- 出産後の届出で出産した被保険者と出生した子が別世帯の場合、親子関係が確認できる書類
後期高齢者医療制度移行に伴う軽減(特定世帯・特定継続世帯)
後期高齢者医療制度に移行する人がいることにより、国保被保険者が1人の世帯となる場合、保険料の平等割額が5年目までは2分の1軽減となり、6年目以降は4分の1が軽減となります。
普通徴収と特別徴収
国民健康保険税は、4月から翌年3月までの1年分を年間の保険税として計算し、各納期までに納付していただきます。
納付方法として、普通徴収と特別徴収があります。
普通徴収
年間の保険税を7月から翌年2月までの8期に分けて納付していただきます。
現金による窓口納付か、口座振替による納付の方法があります。
特別徴収
4月、6月、8月、10月、12月、2月の年金から国民健康保険税を引落しさせていただくものです。
次の3点すべてに該当する方は、年金からの特別徴収をさせていただくようになっております。
- 世帯主が国民健康保険の被保険者であること
- 世帯内の国民健康保険の被保険者全員が65才〜74才であること
- 世帯主の年金額が年額18万円以上で、介護保険料と国民健康保険税の合計が、年金額の2分の1を超えていないこと
(注意) お誕生日や資格取得の時期などによって、特別徴収の開始月が異なりますので、開始通知書などをご確認ください。
なお、特別徴収の方で要件を満たす方は、特別徴収を止め、口座振替で納付することができます。
希望される方は、通帳と通帳の届出印を持参のうえ、町民課賦課徴収係(1階3番窓口)で手続きをお願いします。(特別徴収のままでかまわない方は、この手続きは必要ありません。)
この記事に関するお問い合わせ先
〒289-0692 千葉県香取郡東庄町笹川い4713-131
電話番号:0478-86-6073
ファックス番号:0478-86-4051

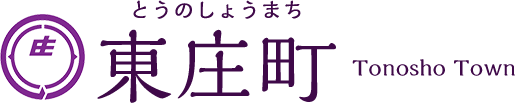

更新日:2025年12月08日