天保水滸伝
「利根の川風袂に入れて月に棹さす高瀬舟」
浪曲や講談で有名な「天保水滸伝」は、土地を潤す利根川と共に、昔から語り伝えられてきた東庄が舞台の、笹川繁蔵と飯岡助五郎、二人の侠客の勢力争いの物語。

"大利根河原の決闘"を描いた「於下総国笠河原競力井岡豪傑等大闘争図」
勢力富五郎が中央に大きく描かれている(芳虎画、1864年/船橋市西図書館蔵)
笹川繁蔵物語
笹川繁蔵は、文化7年(1810年)下総国須賀山村(香取郡東庄町)に生まれた。生家は代々醤油と酢の醸造をしてきた村きっての物持ちで、繁蔵は幼少のころから漢字や数学、剣などを著名な師について学び、人間的にも優れた人物だったと言われる。
繁蔵はやがて相撲取りになるために江戸へ出たが、一年ほどで村へ帰る。その後賭場通いを始め、ほどなくして当時笹川の賭場を仕切っていた芝宿の文吉から縄張りを譲り受け笹川一家を張ることになる。
一方、相模国三浦郡公郷村(神奈川県横須賀市)に生まれた飯岡助五郎は、出稼ぎ先の飯岡の漁港で網元として成功し、繁蔵と同様、博徒の親分として下総一帯に勢力を誇っていた。繁蔵が勢力を増すに従い、助五郎も黙ってはいられなくなった。
天保15年(1844年)、飯岡側が最初の斬り込みを行った。これが大利根河原の血闘である。
この争いは笹川方の圧勝に終わった。しかし当時助五郎は、博徒でありながら十手持ちでもあった。
飯岡側の「御用」の二文字を前に、繁蔵は子分に金品を分け与え、自身は笹川を離れることになった。
初秋の大利根を後に旅立ってから3年。弘化4年(1847年)春、繁蔵は飄然と笹川へ帰ってきた。いっそうの風格を身につけて戻ってきた繁蔵のもとへ、ぞくぞくと昔の子分たちが集まってきた。以前にも増して勢力を持った笹川一家。しかし、飯岡助五郎は密偵を笹川に放ち、繁蔵謀殺の機会をうかがっていた。
弘化4年7月4日。賭場帰りの繁蔵は、ビヤク橋で飯岡側の闇討ちにあい殺害された。
笹川繁蔵、38歳の男盛りだった。
延命寺

笹川山と号する真言宗智山派の寺。笹川繁蔵の碑や剣客・平手造酒、勢力富五郎の墓などがある、天保水滸伝ゆかりの場所でもある。
笹川繁蔵の碑(延命寺内)

昭和15年地元の有志が、繁蔵を偲んで建造。昭和7年に銚子の町で発見された繁蔵の遺骨が葬られている。
平手造酒の墓(延命寺内)

紀州の浪人で、繁蔵の客人として大利根河原の血闘に加わり、義理と人情の最期をとげた。
笹川繁蔵最期の跡

飯岡助五郎一味の成田甚蔵、三浦屋孫治郎らの闇討ちにあい笹川繁蔵が最期をむかえた場所、ビヤク橋のたもとに建つ。
勢力富五郎自刃跡(金比羅山)

地元の方々が建立した「勢力霊神の碑」
繁蔵の子分であった勢力富五郎が、繁蔵の死後、飯岡側に報復しようとするも果たせず、500人の追っ手に囲まれ自害した地。それから「勢力山」と言われている。
天保水滸伝遺品館

笹川繁蔵愛用のキセルや、平手造酒愛用の徳利など、当時の侠客の風俗を語る遺品が展示されている。
この記事に関するお問い合わせ先
〒289-0692 千葉県香取郡東庄町笹川い4713-131
電話番号:0478-86-6075
ファックス番号:0478-86-4051

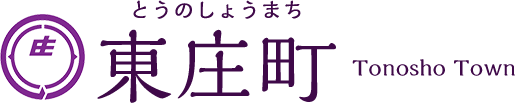

更新日:2022年09月29日