ひとり親家庭の医療費助成
ひとり親家庭等医療費等助成事業は現物給付方式(受給券方式)に変わります!
令和2年11月1日から、千葉県内の医療機関を受診する際、窓口に保険証とひとり親家庭等医療費等助成受給券を提示することで、自己負担金が無料となります。(注意:一部医療機関を除く)県外の医療機関受診分については、引き続き償還払いとなります。
受給券の受取りと利用のイメージは下記ファイルをご覧ください。
ひとり親家庭等医療費等助成事業は現物給付方式(受給券方式)に変わります! (PDFファイル: 757.2KB)
ひとり親家庭等医療費等助成制度とは
ひとり親家庭等医療費等助成制度とは、ひとり親家庭等の方が病気やケガなどをしたとき、安心して病院などを受診できるように医療費の自己負担を助成する制度です。
この制度による医療費等の助成を受けるには、資格認定を受ける必要があり、受給資格者はひとり親家庭等医療費等助成受給券が交付されます。
受給資格者
東庄町に住所があり、健康保険に加入している方で、ひとり親家庭の父また母、養育者及び児童(18歳に達した日以降、最初の3月31日までにある者、また、児童に一定の障害がある場合は20歳未満の者)
ただし、対象となるのは、父または母もしくは養育者および扶養義務者の所得が下表の所得制限限度額未満の世帯です。
| 扶養親族等の数 | 申請者本人の所得額 | 扶養義務者の所得額 |
|---|---|---|
| 0人 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
| 1人 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
| 2人 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
| 3人 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
| 4人 | 3,600,000円 | 3,880,000円 |
| 5人 | 3,980,000円 | 4,260,000円 |
所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)老人扶養親族、特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)がある方についての限度額(所得ベース)は上記の額に次の額を加算した額です。
1.本人の場合は
(1)同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)または老人扶養親族1人につき10万円
(2)特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)1人につき15万円
2.孤児院の養育者、配偶者および扶養義務者の場合は、老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円
3.母、父および児童が受け取る養育費は、養育費の8割を所得とします。
資格認定申請
資格認定申請が必要です。下記の書類を町保健福祉総合センター窓口へご提出ください。
児童扶養手当受給者の方が申請に必要なもの
1.資格認定(更新)申請書(年一回提出 提出してから最初の10月末日まで有効) → 詳細は下記リンク「 書類ダウンロード(分野別一覧)」をご覧ください。
2.申請者及び児童の健康保険の資格情報のわかるもの(次のア~ウのいづれか)
(ア)健康保険証(有効期限内のもの)
(イ)保険者が発行する「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」
(ウ)マイナポータルの健康保険情報
3.銀行等の通帳の写し
4.印鑑
5.児童扶養手当証書
6.子ども医療費助成受給券(高校生までのお子さんがいる場合)
7.子ども医療費助成受給券返納届(高校生までのお子さんがいる場合)
公的年金等で児童扶養手当が停止されている方が申請に必要なもの
1・資格認定(更新)申請書(年一回提出 提出してから最初の10月末日まで有効) → 詳細は下記リンク「 書類ダウンロード(分野別一覧)」をご覧ください。
2.申請者及び児童の健康保険の資格情報のわかるもの(次のア~ウのいづれか)
(ア)健康保険証(有効期限内のもの)
(イ)保険者が発行する「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」
(ウ)マイナポータルの健康保険情報
3.銀行等の通帳の写し
4.戸籍謄本
5.養育費に関する申告書
6.印鑑
7.子ども医療費助成受給券(高校生までのお子さんがいる場合)
8.子ども医療費助成受給券返納届
申請時の注意点
子ども医療費助成受給券の交付を受けている方
現在、子ども医療費助成受給券を所有している場合は、受給券の返還が必要です。返納届と子ども医療費助成受給券を町保健福祉総合センターへご提出ください。
(注意)二重交付を避けるため、子ども医療費助成受給券の返納がない場合は、本券は交付できません。
重度心身障害者医療費助受給券の交付を受けている方
ひとり親医療費助成受給券の交付は受けられません。引き続きご利用ください。
ご注意ください
受給券が重複している場合、適切な医療費助成が受けられない場合があります。
受給券
申請後、審査の上、決定通知と一緒に「ひとり親家庭等医療費助成受給券」を郵送にて交付いたします。
有効期間
受給券は申請のあった月の翌月から利用できます。
毎年8月頃(児童扶養手当現況届時期)に更新の手続きが必要です。
助成の方法
| 区分 | 負担額(令和2年11月受診分から) |
|---|---|
| 入院 | 食事療養費標準負担額及び生活療養費標準負担額 |
| 通院 | 0円 |
| 調剤 | 0円 |
| 証明手数料 | 200円 |
- (注意)令和2年10月以前に受診した医療費については従前の制度(診療報酬明細書1件につき1,000円の自己負担額)が適用されます。
- (注意) 診療・調剤報酬明細書にかかる証明手数料を支払った場合、1件につき200円までは助成されますが、200円を超えた分については、自己負担になります。
助成の方法
千葉県内の医療機関を受診した場合
医療機関の窓口でひとり親家庭等医療費助成受給券と健康保険証を提示してください。保険診療分の自己負担額が無料となります。
千葉県外の医療機関を受診した場合または、受給券を忘れて受診した場合
医療機関の窓口で医療費をお支払いした場合は申請により助成します。下記書類をご提出ください。
1.給付申請書 → 詳細は下記リンク「 書類ダウンロード(分野別一覧)」をご覧ください。
2.医療機関を受診した申請者または児童の健康保険の資格情報のわかるもの(次のア~ウのいづれか)
(ア)健康保険証(有効期限内のもの)
(イ)保険者が発行する「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」
(ウ)マイナポータルの健康保険情報
3.領収書
4.印鑑
5.振込口座のわかるもの
- (注意)領収書に保険点数が記載されていない場合は、医療機関で証明をしてもらいます。
- (注意)医療費等を支払った日の翌月から2年間申請が可能です。ただし、所得要件を満たしていない期間に支払った医療費については、給付の対象外になります。
受給資格の変更
婚姻等により資格が喪失したとき、氏名、住所、健康保険等の申請内容に変更があった場合は届出が必要です。
この助成制度を利用する前にご確認ください
一定額をこえる医療費を支払った場合は、加入している健康保険の各種助成制度を優先
して支給を受け、その後、本制度の申請となります。
なお、喘息などの特定疾病に関しては保健所に申請し助成金の支給を受けることとなります。
この記事に関するお問い合わせ先
〒289-0612 千葉県香取郡東庄町石出2692-4
電話番号:0478-79-0792
ファックス番号:0478-80-3112

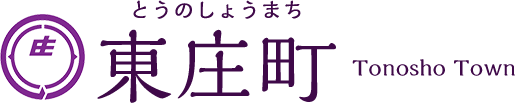

更新日:2025年08月15日